ナレッジ概要
精油(エッセンシャルオイル)は、植物の花、葉、果皮、果実、心材、根、種子、樹皮、樹脂などから抽出した天然の素材で、有効成分を高濃度に含有した揮発性の芳香物質である。(日本アロマ環境協会HPより)
精油を抽出する方法でもっとも一般的に世界中で使用されているのは水蒸気蒸留法である。現在多くの精油製造者では100㎏~200㎏の原料を一度に蒸留するための蒸留器が使用されているが、1台数百万円を超えるものも多く、その初期投資が難しい人々にとって参入しづらい現状がある。
scent letterの採用している蒸留器は一般的な水蒸気蒸留法による精油製造という点では従来のものと同じであるが、蒸留機本体はすべてホームセンター等で揃えることができるパーツによって構成されていることから、簡単な溶接技術があれば自前での作成も可能であり、製造コストも従来の蒸留器の10分の1以下である。身近なところで手に入るパーツを使用しているため、修理やパーツ交換が容易かつひとりでおこなうことができる。また、蒸留時の熱源には薪を使用することができるため、電気やガスなどがない地域でもscent letterの蒸留システムは導入可能で、その汎用性の高さが特徴である。
背景(歴史・発展)
精油抽出の歴史は、中世アラビアの医師、イブン・シーナ(980年〜1037年)まで遡る。それまで行われていたバラのアロマウォーターの抽出をベースに工夫を重ね、「水蒸気蒸留法」を確立したのが始まりとされている1)。
日本では古くよりお香による香りの文化が形成されてきたが、江戸時代には蘭引(らんびき)と呼ばれる香りの抽出器が存在していた。この蘭引は現代でも使用されている水蒸気蒸留法と同じ原理で香りの抽出がおこなわれている。水蒸気蒸留法はその汎用性の高さから世界中で現在も主流の精油抽出法として活用されているが、最近では水蒸気蒸留法のような過熱を必要としない超臨界二酸化炭素抽出法などの新たな技術の活用による精油抽出もおこなわれ始めている。
具体的技術(製法、作業方法、実施方法等の具体的なナレッジの方法)
水蒸気蒸留法は熱によって発生させた水蒸気を植物などの原料に当てることで原料から芳香成分を放出させ、その芳香成分を冷却することで液状の精油として抽出する手法である(図1)。

scent letterが導入する蒸留器は、ステンレス製の容器が上段と下段にわかれる2層構造になっており、下段に水、上段に原料をいれ使用する(図2)。上段の容器の底はメッシュ構造になっており、下段の水が熱せられることで発生した水蒸気はそのメッシュ構造を通過し上段の原料に当たる(図3)。水蒸気に当てられることで植物の組織が破壊され、内包されていた芳香成分が水蒸気中に放出される。放出された芳香成分は水蒸気と共にパイプ内を運ばれ、冷却管内を通過していく(図4)。冷却管内はパイプがらせん状になっており、その周囲を冷却水が循環している(図5)。らせん状を通過する過程で芳香成分を含んだ水蒸気は熱置換により冷却され、気体から液体に変化し、パイプを抜けオイルセパレーターに徐々に溜まっていく。芳香成分は脂溶性の油分であるため徐々に水と分離し、2層になる(図6)。ほとんどの精油は水よりも比重が軽いため上方に分離していく様が確認できる。




scent letterの蒸留器はホームセンターで手に入れることができる材料で作成可能であることから、初期投資を抑え比較的低コストで事業をスタートできる蒸留器を採用している。そのため、途上国の零細農家のような金融機関等からの借り入れが難しいコミュニティでも溶接技術があれば導入可能である。蒸留機本体の故障や劣化による部品交換は周辺で手に入りやすいもので代替可能なため、管理やメンテナンスが容易であることが大きな特徴である。
ナレッジ活用事例
scent letterの蒸留器はホームセンターで手に入れることができる材料で作成可能であることから、初期投資を抑え比較的低コストで事業をスタートできる蒸留器を採用している。そのため、途上国の零細農家のような金融機関等からの借り入れが難しいコミュニティでも溶接技術があれば導入可能である。蒸留機本体の故障や劣化による部品交換は周辺で手に入りやすいもので代替可能なため、管理やメンテナンスが容易であることが大きな特徴である。
日本における位置づけ・特徴
水蒸気蒸留法は今後も引き続き主流の精油抽出法であることに変わりはないと思われるが、マイクロ波を活用した蒸留器や超臨界二酸化炭素抽出法などの新技術を用いた蒸留手法を導入する施設も出始めている。
水蒸気蒸留法を採用するメリットとして挙げられるのが精油だけでなく芳香蒸留水という芳香成分を含んだ水が採取できるという点である。芳香蒸留水は水蒸気を用いて蒸留する方法でのみ得ることが可能であり、精油の数10倍の収量があるといわれている。化粧品の原料や最近だとサウナのロウリュなどでの使用が広がり始めている。芳香蒸留水もうまく製品として活用することで他の抽出法では得ることができない商品ラインナップや新たな販路を精油事業者が開拓する可能性を秘めている。そのことからも、水蒸気蒸留法を用いた精油抽出は今後も一定の需要があると考えられる。
ナレッジの所有者・継承者および連絡先
- 日向工房
https://hinata-lab.com/aroma.html - scent letter株式会社
https://scent-letter.co.jp/scentofrebirth/
関連URL
引用・参考文献
- アロマセラピー標準テキスト 準テキスト 基礎編(丸善株式会社)(日本アロマセラピー学会編),(2008)
その他
執筆者
長壁 総一郎(scent letter株式会社)

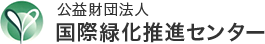
コメントする