ナレッジ概要
食品の保存は人類の歴史とともに発達してきたナレッジのひとつである。民族の食習慣や居住地域の気候、生息する動植物の種類等によって保存方法は異なるので、必ずしも日本のナレッジが世界で通用するとは限らない。ここでは日本の伝統食品の例を参考に、商品保存の原理や考え方をまとめる。
背景(歴史・発展)
狩猟中心の生活から農耕を取り入れるようになると、食品を保存することが必要になった。保存は微生物による食品の腐敗を防ぐことで、においや味の劣化を防ぐとともに、微生物や有害物に由来する病気を予防し、健康な生活が維持できる。微生物の活動を抑えるためには食品の水分を下げることが簡便、有効である。天日と風に晒して乾物やひものが作られる。また、塩漬けもよく行われる脱水方法のひとつである。高塩分の浸透圧を利用して、微生物が利用可能な自由な水分量(活性水分)を下げる。高温多湿な日本では、梅干しや漬物など塩蔵食品が多い。ハムなどの燻製品も、燻蒸の前に塩漬け処理をしている。その他、微生物による発酵も食品の加工とともに保存方法である。発酵と腐敗はどちらも微生物活動であるが、主に食品中の糖質が微生物の酵素により分解、アルコールや有機酸が生成するのを発酵という。これにより、味や風味、栄養価が高まる。一方、主にタンパク質やアミノ酸が分解し、硫化水素やアンモニアが生成し、悪臭が発生する場合を腐敗という。発酵と腐敗は人間の都合で区別しているだけで、どちらも微生物の作用である。発酵に利用する有用な菌を増殖するため、蒸したコメなどに菌を接種し増殖させたものは麹である。このほか、砂糖漬け、高野豆腐のような凍結乾燥等による保存法もある。いずれも菌が繁殖できる水分を減少させる方法である。いずれも地域の気候条件を考慮して適切な方法を選択する。
具体的技術(製法、作業方法、実施方法等の具体的なナレッジの方法)
1) 乾燥
食品を乾燥して微生物の活動を抑える。日本語では植物性の材料は乾物(わらび、干しシイタケ、昆布)、動物性の材料は干物(目刺し、アジ)と呼ばれることが多い。伝統的には天日であるが、時間がかかるので最近は機械(熱風乾燥)で干すことが多い。生のまま干しこともあるが、ゆでたり焼いて干す場合もある(煮干しなど)。内臓は傷みやすいので取ってから干すこともある。干し方によって、丸干し、開き干し、みりん干し、素干しなどと区別される。乾燥することにより栄養分が濃縮したり、カルシウムや食物繊維等の含有率が増加したり、干しシイタケのようにビタミンDが生成したりするので、一般に生より栄養価が高い。

2) フリーズドライ(真空凍結乾燥)
食品の乾燥法で、日本ではインスタント味噌汁やカップ麺のかやく等で普及している。もともとは1950年代にアメリカで軍隊の食料の食味改善を目的に開発された方法である。食品を冷凍し、形状を保ったまま、真空状態で乾燥することにより、常温長期保存が可能となった。また、軽量化、輸送性が改善された効果も大きい。食品を−30℃以下で急速冷凍することにより氷の結晶化を抑える。その後、真空容器に入れ減圧で脱水することで、氷が水に融解することなく、真空下で直接気化して脱水する(昇華現象)。メリットは、低温で乾燥するので、品質劣化が少なく、色や香りなどが保たれやすい。多孔質な状態に脱水するので、内部まで乾燥する。復元時に形状を保つ。デメリットとしては硬さなど物理的食感が劣ることや、減容しないのでかさばること、設備投資と電力が必要でコストがかかることである。

3) 塩保存、燻製
塩(NaCl)に漬けることにより、浸透圧により食物から脱水し、微生物が利用できる水分(水分活性AW)を下げることで腐敗を防ぐ方法である。梅干しやぬか漬け、塩鮭などがある。伝統的な塩分濃度は10~20%であり、塩蔵期間中にうまみのアミノ酸類が加わる効果も期待される。最近は健康のため減塩志向があり、4~7%と低い濃度で作られることがあるが、その場合は保存性がわるく、冷蔵保存が必要である。また、別途調味料を加えることが多い。さらに、水中なので酸素との接触が抑えられたり、乳酸発酵により酸性になることも保存性を高めている。
秋田の燻りがっこ、ハム、ベーコンなどは塩蔵とスモークを組み合わせて貯蔵性にとともに風味や食味を高めたものといえる。スモークに用いる樹木の種類で微妙に味が変わる楽しみもある。

4) 発酵
発酵は、食品に有用な微生物を作用させることによって人の嗜好性にあったアルコールや有機酸類を生成させて食味を向上させるとともに、保存性を高める方法である。微生物の作用によりアンモニアや硫化水素など人間にとって悪臭成分が生成する場合は腐敗と呼ばれる。一般に、発酵はでんぷんや糖類が微生物の酵素で変質し、腐敗はタンパク質やアミノ酸が変質することが多い。漬物は塩分により水分活性が低下するとともに、乳酸発酵による酸性化、空気の遮断も保存性を高める要因である。特定の有用な微生物を優先的に培養するため、コメなどのでんぷん質で菌や酵母を培養し、発酵の菌種とすることもある。なお、菌類は対象国に生息する菌を利用することが適当である。

5) その他
微生物の繁殖を制限できるよう水分活性を下げる方法としてジャムのような糖度を高める方法もある。フリーズドライと同様の方法であるが、高野豆腐、凍み豆腐、凍みこんにゃくのように、凍結した商品を、機械を使わず冬の乾燥した大気中で脱水する方法もある。
ナレッジ活用事例
日本の保存食に例と保存方法を以下にあげる。
- 北海道:鮭のルイベ(凍った鮭):冷凍
- 秋田:いぶりがっこ(燻製した大根の漬物):燻製、塩蔵
- 伊豆諸島:くさやの干物(新鮮な魚を漬け込み液につけ、乾燥させる):塩蔵、乾燥
- 奈良県:奈良漬:塩蔵、発酵
- 滋賀県:鮒ずし:発酵
- 儀式・神事:熨斗鮑(のしあわび):昆布、乾燥
日本における位置づけ・特徴
日本は発酵食品の先進国といわれる。これは日本の風土が温暖で湿潤なため、多くの菌類が繁殖しやすい環境にある。一方、多くの菌類叢の中から発酵に適した菌を選抜し、食品の保存性と品質向上に利用してきた。乾燥地では環境に生息する菌類が少ない。そのため、乾燥による保存が主流になっている。レーズンなどのドライフルーツは中近東や地中海性気候の地域で生産される。日本のナレッジが直接適用できる地域は日本の気候に近い地域が適当である。
関連URL
引用・参考文献
- 農林水産省(2022) aff 2022, 11月号、日本の食文化01
https://www.maff.go.jp/j/pr/aff/2211/spe1_01.html - ミツカン水の文化センター事務局(2016) 『水の文化』52号

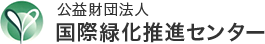
コメントする