ナレッジ概要
漆製品はアジア諸国でも見られるが、高品質な工芸品はJapanとも呼ばれ、代表的な日本の工芸品である。工芸品の漆器製造は、木地、漆塗り、加飾(蒔絵)の工程に分かれ、それぞれ担当の職人や工房による分業体制がとられることが多い。漆掻き、精製、素地、塗り、加飾の工程を経て工芸品が完成する。日常品はプラスチック等に置き換わった部分もあるが、伝統的な工芸品の価値が再評価されつつある。タイやミャンマーの漆器は日本の過去の技術指導によって途絶えつつあった技術が継承されたものである。ただし高度な技術であるがゆえに、後継者問題を抱えている。
背景(歴史・発展)
漆はウルシ属ウルシ科の木本植物ウルシ(和名)(学名Toxicodendron vernicifluum, またはRhsa vernicifera)の樹液から作られる天然塗料で、これを食器や家具などに塗布し、強度や防腐性を高めるとともに、色付けや装飾性を加味したものである。中国や朝鮮半島でも同種のウルシが分布し、日本と同様に樹液を天然塗料として利用さている。日本では縄文時代の遺跡(青森県是川遺跡や東京都下宅部遺跡、福井県鳥浜貝塚など)からウルシを塗布したものが出土している。金沢大学等の調査では約7000年前の中国浙江省の田螺山遺跡などでもウルシの塗布が確認されているので、漆の正確な起源はわからない。タイやミャンマーなど別種のウルシ科の樹木(Melanorrhoea usitata, またはGluta usitata)による漆器が作られている。東南アジアでは広く漆が使われていた。日本のナレッジとしては単なる天然塗料ではなく、工芸品として発達した高度な加工技術にある。
平安時代ころから国内では漆を塗布した工芸品としての進化がみられる。漆は仏具や仏像、武具に用いられるようになり、加工技術が高まるとともに、大規模な城郭や御殿、霊廟建築などにも使われ、大量に漆が必要となった。そのため、南蛮貿易により中国や東南アジアから生漆が輸出された記録が残る(北野ら 2014)。漆製品は交易品としてヨーロッパに輸出され、ベルサイユ宮殿などにも収蔵されている。鎌倉時代には高蒔絵など造形技術が発達し、江戸時代には各地の藩諸大名が漆産業を育成したため、日本各地に生産地が形成された。明治以降は海外の博覧会に出品されて精巧な漆工芸の知名度はさらに高まった。
漆はかつて日常的な食器などに利用されていたが、第二次大戦以降、工業製品である安価なプラスチックや金属製品におきかわってしまった事情は日本に限らず東南アジア諸国でも同様であった。その結果、日本の漆製品はますます工芸品に限定されるようになり、精緻な技術が結集した高価なものとなった。
工芸品の漆器製造は、木地、漆塗り、加飾(蒔絵)の工程に分かれ、それぞれ担当の職人や工房による分業体制がとられている。そのため、集団としての後継者育成が必要で、ナレッジの継承には苦労している。

具体的技術(製法、作業方法、実施方法等の具体的なナレッジの方法)
漆掻き
ウルシの木から漆を取る作業は漆掻きと呼ばれる。春の芽吹きが落ち着いた初夏から漆掻きは始まる。漆掻き職人はカンナと呼ばれる専用の刃物を使い、ウルシの幹に数センチの「辺」(掻き傷)を付ける(「目立て」作業)。その後、約4日から1週間間隔で徐々に長い「辺」を付けていく。滲み出てくる漆は専用のヘラで掻き採る。季節によって塗りの際の硬化速度や透け具合などの性質が異なるため、初夏の初漆、盛夏の盛漆、晩夏の末漆などと区別される。秋の落葉の頃になると、幹を一周するほどの長い辺を付けて一年のシーズンを終える(「裏目掻き」)。

精製
このように採取した生漆(きうるし)は精製工程をへて塗るための漆ができる。「精製生漆」「精製透漆(すきうるし)」「精製黒漆」と分類される。「精製生漆」は原料の生漆(きうるし)からゴミなどを取り除いたものをいい、塗り工程における下地や拭き漆仕上げの際に使用する。拭き漆仕上げとは、精製生漆を塗っては拭き取る作業を繰り返し、木目などを表現として生かすための手法である。 「精製透漆(すきうるし)」は原料の生漆に対してナヤシとクロメと呼ばれる加工を行って、ゴミやチリを取り除いたものをいう。ナヤシは漆の液体をかきまぜて成分を均一にする作業のことで、クロメはナヤシのあとに漆の液体を加熱して40℃前後に保ちながら少しずつ水分を蒸発させる作業をいう。「精製黒漆」は原料生漆にナヤシとクロメの作業を行う際に、鉄粉(水酸化鉄)を混ぜたもので、漆の成分と鉄イオンが化学反応によって黒色に変化させたものをいう。クロメのあとには再度ゴミやチリを取り除く。黒色以外の朱色や白漆などは「精製透漆」に顔料を入れて作る。漆本来の色は原料生漆の段階では茶褐色であるが、精製加工により様々な色が作られている。
「精製透漆」と「精製黒漆」は、油分を加えて上塗り用としたり、油分を加えないで上塗りの後に磨いて仕上げる研磨用漆などに分類される。

素地
漆器の素地には木製品と合成樹脂製品がある。木製品のうち、椀などの丸物は天然木をロクロで回しながら削って形をつくる。天然木は大きめな形状にあらく切り出し、6ヶ月から1年かけて乾燥させたものを使う。箱、盆などの角物や板物は、板の状態で約1年乾燥させてから裁断し、削り込み、組み立てる。プラスチック樹脂の製品は木や合成樹脂の粉を機械で熱加工してつくられる。
塗り
塗りの工程は下塗りと上塗りとに分けられる。下塗りは、漆器の強度など品質を左右する部分で、「塗り」、「乾燥」、「研ぎ」を何度も繰り返す。上塗りは、均一の厚さに仕上げる熟練の技が求められる。また、漆を乾燥させるための一定の温度、湿度を維持する必要がある。下塗りから上塗りまでは3ヶ月以上の期間をかける。塗りの方法は、器の形などに応じて、はけを使った手塗りのほか、スプレーガンを使って塗料を吹き付ける方法もある。
加飾
漆器を彩る加飾には伝統的な沈金(ちんきん)と蒔絵(まきえ)がある。沈金は、刃物で絵柄を彫り、その彫り跡に金箔・銀箔、金粉・銀粉、顔料等を漆で接着して仕上げる。蒔絵は、漆を含ませた筆で模様を描き、そこに金粉・銀粉などを蒔きつけ、研ぎ・磨きを繰り返してつくる。こうした技法のほか、スクリーン印刷など比較的容易で一度に多くの加飾ができる技法も使われる。蒔絵の絵柄や文様は、伝統的には鶴や亀、自然をモチーフにした図案が多い。
漆の主成分はウルシオールという化学物質であり、それが固化して丈夫な塗布面ができる。固化にはウルシオールにラッカーゼという酸化酵素が作用する。ラッカーゼを活性化するためには適切な温度(25℃前後)と湿度(70~80%)条件が必要であり、現代の塗料とは異なる。

ナレッジ活用事例
1950年代、タイ国では北部チェンマイなどに漆器職人わずかに残る程度でその技術は消滅しつつあった。タイ政府は技術の復興を願い、工業省が国際機関の支援を受けて日本の技術者(生駒弘氏ら)を招聘し、1957年から4年にわたり技術者養成が組織的に実施された記録がある(西田 2020)。この事業により多くのタイ人の漆職人が育成された。その中心となった生駒弘氏は伝統工芸よりも現代的なデザインを重視した。そのため、木地デザインの制作者も日本から招聘し、輸出も視野にいれた漆市場の開拓をタイ政府に提案した。その後、大山八三郎氏が民営の漆工房をタイに作り、日本の伝統を受け継いだ精緻な工芸品を作成し、観光客の人気を博した。
ミャンマーでも日本の工芸家や大学による技術移転が2000年代に行われている(松島 2008)。ミャンマーの中央部のバガンには漆芸大学があり、日本の東京芸術大学、宇都宮大学によってワークショップによる交流がすすめられた。しかし、現在は政情不安や軍事クーデターがあり、中断されたままになっている。
東南アジアの多くの国で漆器は工芸品の高額な商品として生産されているが、その発展には上記のような日本の漆関連のレッジの技術移転が貢献している。一方、現地には蒟醤(きんま)技法(漆の塗布面に、刃物で細かな彫り傷をつけて、色漆や顔料をその傷の中に埋め込み文様を表現する技法)の職人が多かった。日本との技術交流でお互い刺激をうけながら各々の技法の習得が行われており、一方的な技術移転ではない協力関係が築かれてきた点も注目される。
日本における位置づけ・特徴
現在、日本漆器協同組合連合会に所属団体している団体産地は、青森県津軽塗、秋田県川連漆器、宮城県鳴子漆器、福島県会津塗、東京都江戸漆器、長野県木曽漆器、新潟県村上堆朱、富山県高岡漆器、石川県輪島塗、石川県山中漆器、石川県金沢漆器、福井県越前漆器(河和田塗)、和歌山県紀州漆器、香川県香川漆器、宮崎県宮崎漆器が所属し、これ以外にも神奈川県の鎌倉彫、小田原漆器、沖縄県の琉球漆器、京都の京漆器などがある。それぞれ地方の産地ごとの特色をいかした工芸品が作られている。輪島塗にみられるように、制作工程は複雑で多岐にわたるので、通常は分業体制がとられている。
ナレッジの所有者・継承者および連絡先
日本文化財漆協会や日本漆器生産協同組合などの団体がある。
関連URL
- アジア漆の造形と祈り―東南アジアの漆― – Urushi
https://asian-urushi.com/2022J.html - 日本文化財漆協会
https://bunkazai-urushi.org/ - Asian Lacquer Craft Exchange Research Project
https://asian-urushi.com/index.html
引用・参考文献
- 北野信彦・小檜山一良・竜子正彦・本多貴之・宮腰哲雄.桃山文化期における輸入漆の調達と使用に関する調査(Ⅲ) 2014⦆―日本国内の出土漆器における輸入漆塗料の使用事例― 保存科学 53:67-79
- 西田昌之(2020) チェンマイ漆器の復興と産業化 ―1957~1961年漆芸家生駒弘による技術移転を巡って― タイ研究No.20, 1-23. 日本タイ学会
- 松島さくら子(2008) ミャンマーにおける漆工芸を通した工芸教育交流
―ミャンマー伝統工芸学術支援事業の活動現場から―、宇都宮大学教育学部紀要 58:181~191

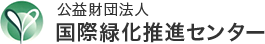
コメントする